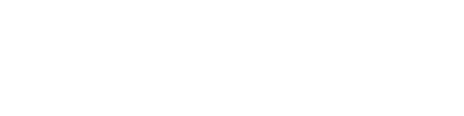農薬の安全性評価の状況
規制行政、関連法令
化学農薬は、その使用者や消費者にとって十分に安全でなければなりません。また、環境への影響も最小限であることが求められます。さらに、効果が確実でなければならず、農業者にとって使いやすいものでなければなりません。加えて、費用対効果も重要であり、農業者が使わなければ意味がありません。これらを実現するため、農薬製造企業は幅広い分野の科学を活用しています。
農薬製造企業は、製品の開発から上市までの過程において、経済協力開発機構(OECD)などの国際的組織で認められた最新の試験方法や試験施設に関する基準(GLP制度)に従い、自らの製品のヒトに対する安全性や環境への影響を確認しています。そして、責任を持って安全性が高く、効果のある製品だけを世の中に提供しています。
農薬は、生物に対して生理活性を持ち、環境に意図的に放出されるため、農薬の安全性を確保するために、関連法令や所管官庁による規制行政が行われています。
(月刊 化学物質管理 2022年4月号)
● 農薬取締法(農林水産省)
-
粗悪な農薬を追放し、農薬の品質保持と向上を図り、ひいては食料の増産を推進することを目的に1948年に制定。その後、科学技術の進展や社会的関心の変化等を踏まえ、累次にわたり改正。1971年改正では、目的規定が新設され、2018年改正によろ法の目的は次の通り「(目的)第1条:農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。」
-
● 食品安全基本法(内閣府)
-
食品の安全性確保に関する施策を総合的に推進することを目的に制定。農薬の食品健康影響評価(ADI、ARfDの設定など)を行うリスク評価機関である内閣府食品安全委員会が設置された。
-
● 食品衛生法(厚生労働省、消費者庁)
-
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的として制定。ポジティブリスト制度の導入はこの法律の改正による。2024年4月より、残留基準の設定は消費者庁、食品残留の監視は厚生労働省が管轄。
-
● 毒物及び劇物取締法(厚生労働省)
-
毒物及び劇物 について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律。
-
● 水道法(基準関係)(環境省)
-
水道水の水質基準を定める。浄水で検出される可能性の高い農薬類が対象農薬としてリストアップ。関連通知でゴルフ場からの排水中の農薬濃度の指針値が定められている。
-
● 環境基本法(環境省)
-
水質汚濁に関する環境基準(環境基準健康項目、要監視項目)、土壌の汚染に係る環境基準、地下水の水質汚濁に係る環境基準では、各種の農薬について基準値が定められる。関連通知で、水質汚濁に関する要監視項目、要調査項目が定められている。
-
● 水質汚濁防止法(環境省)
-
公共用水域の水質汚濁の防止に関する法律。河川、湖沼、港湾、かんがい用水路等の公共用水域での排水基準を定めている。
-
● 廃棄物処理法/廃掃法(環境省)
-
廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。農薬の空容器は材質にもよるが産業廃棄物に分類、法律に則って環境汚染の原因とならないよう適正に処理する義務がある。また、使用残農薬は産業廃棄物に分類され、許可を受けた廃棄物処理業者に回収処理を委託することが必要。
-
● 消防法(総務省)
-
農薬の中には、有効成分の性質や有機溶剤や乳化剤などの補助成分の性質から危険物に該当するものがあり、製造・取扱・運搬・貯蔵などについて、消防法による規制を受ける。
-
● 化管法(経済産業省)
-
農薬の有効成分で第一種指定化学物質・第二種指定化学物質に指定されたものは、PRTR制度、SDS制度の対象となる。
-
● 化審法(経済産業省)
-
農薬などの化審法と同等又はそれ以上の評価が要求される他の法令により管理・規制されている化学物質は化審法の規制・管理から除外。
日本における農薬の安全性評価の状況や、各報告に書かれている内容を説明します。
https://www.croplifejapan.org/news/20201030.html
1. 日本における
農薬の安全性評価の状況
農薬は、農薬取締法に基づき、その販売を開始する前に農林水産大臣の登録を受けることが義務付けられています。登録の際、農林水産省は他府省と連携し、ヒトの健康や環境への影響を含むさまざまな分野での安全性に関する審査を実施します。特に、ヒトの健康に直接関わる評価として、内閣府食品安全委員会による「食品健康影響評価」および消費者庁による「残留農薬基準の設定」が行われます。
(1)食品安全委員会による食品健康影響評価
https://www.fsc.go.jp/hyouka/2003年に施行された食品安全基本法に基づき、2003年7月1日、内閣府に食品安全委員会が設置されました。国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもと、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関として設置されたものです。
農薬については、短期や長期の毒性試験、繁殖への影響や催奇形性評価の結果に基づき、管理された使用方法を前提に、ヒトへの安全性について問題がないと判断された場合に、ヒトが一生涯毎日摂取しても影響の出ない量として許容一日摂取量(ADI)、短期間に摂取しても影響の出ない量として急性参照用量(ARfD)を設定しています。透明性を確保するために評価結果や検討した会議の議事録をホームページに公表しています。食品安全委員会が行うこれらの評価方法や試験成績に求める要件は基本的に国際機関や欧米等先進国のそれと同等です。
また、これらの評価対象となる試験成績は、国際的な標準として認められたOECDテストガイドラインに準拠したものです。試験については、同じくOECDのGLP基準に適合していることが確認された信頼性の高い施設で実施が求められています。
*優良試験所規範:Good Laboratory Practiceの略で、化学物質等の安全性試験を行う試験施設に対する認証・監査制度
(2)消費者庁における残留農薬基準の設定
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/消費者庁の食品衛生基準審議会では、農薬が残留する可能性のあるすべての食品からの総農薬摂取量または一日に摂取する最大量が食品安全委員会の設定したADIまたはARfDを超えない範囲で、各食品の残留農薬基準を設定しています。この基準は、食べる量や嗜好などを考慮して、国民全体、幼少児、妊婦などのいずれのグループでも許容量を超えないように規定されています。
この基準設定の考え方は、OECD諸国やCodex等の国際的な手法と整合していますが、食文化の違いに基づく食品ごとの摂取量の違いや、栽培方法や気候の違いに基づく農薬使用方法の違いにより、作物が同じでも国ごとに異なる残留農薬基準となる場合があります。重要なのは、総農薬摂取量等がADIやARfDを超えないことであり、個々の食品の残留農薬基準の大小でその国の安全政策に優劣がつくものではありません。
ちなみに、厚生労働省が全国的に実施しているモニタリング調査の結果では、いずれの農薬でもその摂取量はADIの数パーセントの範囲にとどまっています。
なお、2024(令和6)年4月1日に、食品衛生基準行政は厚生労働省から消費者庁に移管されました。
「食料生産の重要性と農薬の役割」動画チャプター版
チャプター4.科学的データの裏付け
人健康に関する安全性評価がまとめられています。
https://www.croplifejapan.org/labo/movie/
2. 日本における
農薬の環境安全性評価の状況
農薬は、その多くが生理活性を有する化学物質です。その使用によって、防除対象以外の作物、ヒト、環境に何らかの影響を及ぼす可能性があります。
散布方法によっては、圃場外に散布液が飛散するリスクも考えられます。特に、有用生物、周辺作物、住宅地に問題が起こらないように適正に使用しなければなりません。
次に、飛散や田面水からの流亡、土壌中からの流出などにより環境中に拡散した農薬は、水系の水産動植物や水質汚濁のリスクが考えられます。また、作物に散布された農薬が土壌に落下したものは、その多くが土壌表面あるいは土壌表層で分解・消失しますが、土壌表層部に長期間残留するようなことがあれば、後作物へのリスクが考えられます。
環境大臣は、環境影響の観点から農薬を登録するか否かの基準として農薬登録基準を定めています。農薬登録基準には、水域の生活環境動植物(旧:水産動植物)の被害防止、水質汚濁、土壌残留に関する3つの基準があります。
https://www.env.go.jp/water/noyaku.html
適正使用による有用生物であるミツバチの被害防止への取り組みや、水域の生活環境動植物(旧:水産動植物)、水質汚濁、土壌残留のリスクに対して、環境省が設定する農薬登録基準などの規制管理により、農薬の安全性が確保されています。詳細については、動画をご覧ください。
なお、2018年の農薬取締法の一部改正(平成30年6月15日法律第53号)により、
● 農薬登録保留基準 ⇒ 農薬登録基準
● 水産動植物 ⇒ 生活環境動植物
に変更されていますので、ご注意ください。
「食料生産の重要性と農薬の役割」環境編
https://www.croplifejapan.org/labo/movie/
3. 改正農薬取締法(2018年施行)
2020年から使用者安全及び蜜蜂に関する新たなリスク評価法が導入され、2021年度からは最新の科学的知見に基づいた再評価制度が開始されています。農薬は最新の科学に基づいてリスク評価され、登録制度と適正使用が車の両輪となって農薬のリスク管理が行われています。当会の会員は、科学的な評価に必要な試験成績や公表文献の収集・提出などを行っています。
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/
農林水産省:農薬取締法に基づく規制の現状と今後について、
2020 年10 月
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/attach/pdf/index-10.pdf
農林水産省:農薬情報
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/